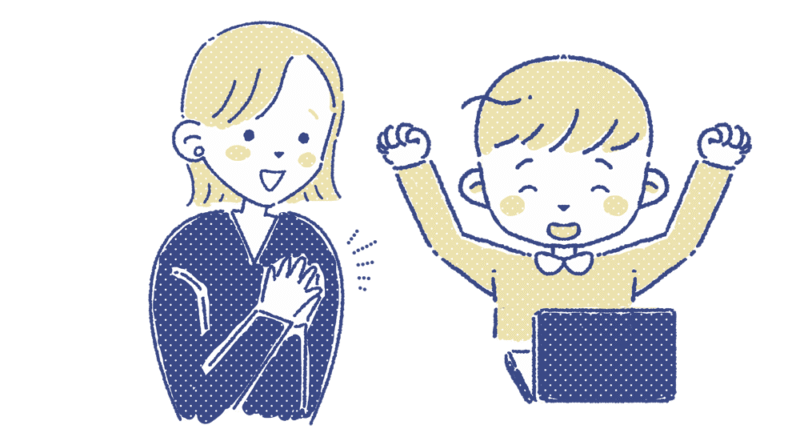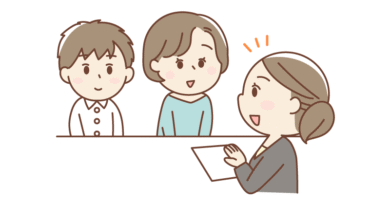教室広報における「見直しポイント」
教室広報における「見直しポイント」
子ども向けのプログラミング教室を始めたものの、
「なかなか体験会に人が来ない」「SNSに投稿しても反応が少ない」
このようなお悩みを抱えていらっしゃる先生も多いのではないでしょうか。
実際に当センターに寄せられるご相談でも、カリキュラムの構築や教材選びよりも、「広報活動をどう改善したらよいか?」というご質問が近年とても増えてきています。
教室の魅力をしっかりと伝えているつもりでも、“伝え方”や“届け方”に少しズレがあるだけで、保護者に正しく届かず、反応が大きく変わってしまうのが広報の難しさでもあります。
今回のコラムでは、広報活動において思わぬ集客ダウンにつながる“落とし穴”と、その改善のヒントについてご紹介します。
見直しポイント①
広告ターゲティングが曖昧になっていないか?
Web広告やSNS広告の出稿が身近になり、利用されるオーナー様が増えてきました。
広告を出稿する場合、ただただ「多くの人に見せれば効果があるだろう」という曖昧な考え方では、広告費コストが無駄に膨れ上がってしまいます。
地域密着型ビジネスであるプログラミング教室の広報では、教室から通える範囲に住んでいる保護者にピンポイントで情報が届くことが重要です。
遠方の方にいくら広告が表示されても、実際には通えない、問い合わせにも至らないというケースが大半です。
以下のことを意識して施策を進めることで、広告費への投資効果の改善が実感できるはずです。
- エリアを意識した(例えば教室の半径○km以内など)ターゲティング設定
- 教育熱心と思われる保護者層を意識したターゲティング設定
- 地元の子育て情報サイト・地域フリーペーパーへの掲載
- Googleビジネスプロフィールに情報を登録し、検索や地図アプリからの流入を増やす
- 教室サイトのSEO対策として「〇〇市 プログラミング教室」などのキーワードを盛り込む
- 交通広告やサイネージ広告など「広く・多く」の層をターゲットにした広告出稿は避ける
また無駄な広告費支出を避けるために、広告ごとの効果測定をきっちりとやっておく必要があります。
事業規模や運営形態にもよりますが、ROAS(売上高÷広告費)はオープン直後や春期などの募集期で300%以下に、通常期では500%以下に抑えるよう施策を熟考していきたいものです。
見直しポイント②
特定の手法だけに施策が集中していないか?
※詳しくは前回の 私のコラム をお読みください。
保護者の情報収集は多様化しています。
「Instagramは更新しているからOK」「チラシは配っているから大丈夫」
このように、特定の手段に偏った広報だけで満足をしていないか、いま一度振り返ってみる必要があります。
現代の保護者は、情報収集を複数のメディアを横断して行うのが当たり前になっています。
たとえば「SNSで教室を知り、Googleで検索して詳細を確認し、地図アプリで場所を調べる」といったように、メディアの「連携」が自然な行動導線となっているのです。
そのため、「SNSだけ」「サイトだけ」「チラシだけ」といった単一媒体に依存するのではなく、
SNS・Web・口コミ・地域メディアを一貫性ある情報でつなげるオムニメディア型」の戦略が必要不可欠です。
見直しポイント③
教室を運営している「人」が見えているか?
保護者が最も気にされることの一つが、「どんな方が子どもを指導してくれるのか」という点です。
それにもかかわらず、講師や教室オーナーの情報がほとんど掲載されていない広報ツールも見受けられます。
特にお子様を初めて預ける場合、不安があるのは当然です。教室オーナーや先生のプロフィールや日ごろの活動をオープンにしておきたいものです。
- 指導歴
- 指導方針
- 資格や経歴
- 顔写真(表情の伝わる自然な写真)
- 子どもとの関わり方に関する一言コメント
さらに、実際の指導の様子がわかる写真や動画があると、信頼感は一気に高まります。
「照れくさいから」「恥ずかしいから」といった理由で、ご自身をオープンにしたがらない先生もいらっしゃいます。
そのお気持ちは理解ができますが、それでも勇気をもって取り組んでいただきたいものです。
見直しポイント④
問い合わせ方法が提示されているか?
教室に関心を持った保護者が、いったいどのようにコンタクトを取ればいいのか、よく分からない広報ツールも目にします。
「電話番号を書いているので電話してくれるはずだ」
「住所を書いているので訪問してくれるはずだ」
そのように一方的に考えていらっしゃるなら、その場合は改善が必要です。
公式サイト内に何らかのメールフォームを作り、そこからのお問い合わせをいただくようご案内するのが一般的な手法です。
また近年では、「LINE公式アカウント」やSNSのDM機能など、個人情報を引き渡さない問い合わせ手法を好む保護者も増えています。
いずれの手段を活用するにせよ、連絡方法は明示しておきましょう。
また、「レッスン体験」などの来校促進についても、保護者への親切なご案内が必要です。
以下のような内容が記載されているか広報ツールを点検してみましょう。
- 何ができるのか(例:自分のキャラクターを動かす簡単なゲーム)
- 有料なのか無料なのか
- 体験可能な時間帯や持ち物
- 対象年齢や初心者対応の有無
- 親の見学・同席の可否
- 駐車場・駐輪場の有無
単に「レッスン体験ができます」だけの告知では、スムーズに来校の誘導ができません。
こうした情報を丁寧に伝えることで、保護者の不安や疑問を先回りして解消でき、体験会の参加率が大きく変わってきます。
見直しポイント⑤
教育成果を伝えられているか?
以前のコラム でも触れましたが、プログラミング教室という分野は、保護者世代が子どもだった頃にはまだ存在していなかった、比較的新しい教育サービスです。
そのため、多くの保護者にとっては、「子どもが通うことで何を得られるのか」を具体的に想像するのが難しいという現状があります。
だからこそ、「教室に通うことでどんな力が身につくのか」という成果を、できるだけ具体的に保護者に示しておくことが大切になります。
以下のような要素が広報ツールで紹介をされているか点検をしてみましょう。
- 生徒の作品紹介(実際のスクリーンショットや操作動画)
- 1年後の成長例(Before→After)
- 保護者や生徒のリアルな声(コメント)
成果が“見える”ことで、教室の価値をより強く伝えることができます。
見直しポイント⑥
「安さ」で差別化していないか?
「近隣の教室よりも安くすれば選ばれるだろう」と思いがちですが、教育サービスにおいては「安さ」だけが魅力とは限りません。
むしろ、安すぎる価格設定は、「内容が薄いのでは?」「講師の質に不安があるのでは?」といった懸念を生んでしまうこともあります。
さらに、根拠のない無理な廉価戦略を導入することは、健全な経営を維持することへの弊害にもなりかねません。
大切なのは、提供する学習コンテンツの価値に見合った適正価格を、しっかりと提示することではないでしょうか。
教育コンテンツの質をしっかりと高めながら、それに見合った適性な受講料を設定することが、経営安定への近道です。
「入学金割引」や「受講料割引」などのキャンペーン施策については、安易な実施は避けたいところです。
恒常的に割引を行っている場合、広報ツールでの表示方法によっては景品表示法の規制に抵触する恐れもあります。
また、特定の時期だけに実施するキャンペーンは、実施時期の直前や直後の申込者が減少する恐れがあります。
さらに、既存の会員からは「自分のときだけ料金が高かった」といった価格差への不満や不信感が生まれるリスクも考えられます。
まとめ
広報施策を策定する上で、「やったほうがいいこと」は本当にたくさんの事例があり、コラムにまとめることは困難です。
しかし「やってはいけないこと」はある程度限られています。このコラムがお教室様からの情報発信を見直す機会になれば嬉しく思います。
こどもICT教育支援センターでは、 教室経営や広報改善に関するご相談 も随時承っております。
気になる点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。