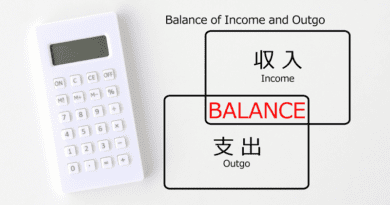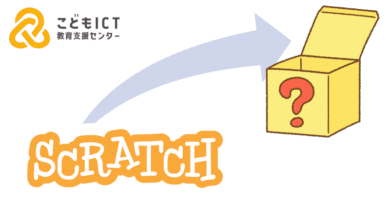教室経営におけるリスク管理を考える
教室経営におけるリスク管理を考える
プログラミング教室の運営を行う場合、子どもの安全確保や法的責任、知的財産の取り扱いなど、幅広いリスクへの対応が求められます。
このコラムでは、教室オーナー様のために、安心して教室を運営するためのリスク管理と法的な留意点を整理してお伝えいたします。
開業形態の選択と法的責任の範囲
プログラミング教室を開設するにあたっては、まず「個人事業主」として始めるか、「法人(株式会社・合同会社など)」を設立するかを選ぶ必要があります。
「個人事業主」として開業する場合は、税務署へ開業届を提出すればすぐに事業を始められます。
設立費用もかからず、経理や申告も比較的簡単なため、小規模に教室を立ち上げたい方に向いています。
「個人事業主」の所得税は累進課税方式で、利益が小さいうちは税負担が軽く済み、さらに青色申告を利用すれば控除や赤字繰越といったメリットも得られます。
ただし、事業上の契約や支払い、トラブル発生時には、事業主本人が無限責任を負い、個人資産にまで影響が及ぶ可能性がある点には注意が必要です。
「法人」を設立する場合は、定款作成や登記といった手続きが必要です。
登記費用など設立コストも発生しますが、事業としての信用が高まり、企業との契約や取引がスムーズになるという利点があります。
法人税は一定の税率で課税されるため、利益が一定規模を超えた場合には、「個人事業主」での運営と比べて税負担が軽くなる場合があります。
また、法人は個人とは独立した存在であるため、負債などのトラブルが生じても会社の財産の範囲内で責任を負う「有限責任」となります。出資者個人の資産まで責任が及ぶことは原則ありません。
ただし、社会保険の加入義務や、決算書の作成・法人税申告といった事務が増える点は考慮する必要があります。
教室開業の場合、開業初期は負担の少ない「個人事業主」としてスタートし、売上や利益が安定してきた段階で法人化を検討されるケースが一般的です。
この場合、法人化のタイミングは、年間利益が概ね500万円を超える頃や、講師の雇用・外部企業との契約が増えるなど事業規模が拡大してきた時期が適しています。
税負担、管理コスト、責任の範囲を総合的に考慮し、自身の教室に最も適した開業形態を選ぶことが大切です。
教室名と商標に関するリスク管理
プログラミング教室を開業される場合、独自の教室名やロゴを設定することになります。
しかし、同一または類似の教室名や、ロゴ画像がすでに他社により商標登録されている場合には、使用停止や損害賠償を求められるリスクがあります。
教室の呼称については、開設前に特許庁の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で商標検索を行い、先行して利用されていないか確認しておきましょう。
また商標登録がされていない場合でも、先行他社と重複した商標を使用した場合、利用者の混乱を招く懸念があります。検索エンジン等で念のため事前にチェックをしておきましょう。
ロゴ等について、安易にインターネット上から流用することは避けたいものです。万が一流用される場合にも、引用元サイトの規定を遵守して行う必要があります。
一度地域に定着した教室名やロゴを変更することは、経営上の大きなリスクとなりますので、慎重に準備を進めていきましょう。
また、将来的に地域を超えての拠点拡大や、オンラインでの広域の展開を見据える場合には、自らの商標を登録しておくこともおすすめします。
こちらのコラムも参考にして下さい。
「新規教室の屋号を考える」
教材・コンテンツ運用と著作権管理
プログラミング教室では、教材テキスト、コード等の解説資料、スライド資料、動画教材など、さまざまなコンテンツを取り扱います。
これらを作成・利用する際には、著作権の扱いを正しく理解しておくことが重要です。
著作権を軽視した教材の利用や配布は、思わぬトラブルや法的責任につながるおそれがあります。
特に次のような行為は、著作権侵害に該当する可能性があります。
- 市販の教材をコピーして授業用に配布する
- インターネット上の画像やコードの解説を無断で使用する
- 他社の教材構成を模倣して独自教材として提供する
また、教材や学習資料を外部講師や制作会社に委託して作成する場合は、作成後の著作権の帰属について、契約書等で明確にしておくべきです。
たとえば、教材の二次利用・再配布の可否、改訂時の権利関係などを事前に取り決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
教室の安全管理
プログラミング教室は室内での活動が中心であるため、一般的には安全な環境と思われがちです。
しかし、子どもを預かる場である以上、運営者には常に安全配慮義務が求められます。
小さな不注意が事故やトラブルにつながることもあるため、日常的な点検とルール整備が欠かせません。
特に注意すべきポイントは次のとおりです。
- 電源コードや配線の整理、転倒防止対策
- 火災・地震などの緊急時に備えた避難経路の確認
- 教室内設備(モニター・PC・照明など)の消毒や安全点検
- 教材や機材の誤使用による事故の防止
万が一の事態に備えて、施設賠償責任保険や受講生傷害保険への加入も検討しておくと安心です。
また事故やトラブルが発生した際に、スタッフそれぞれが異なった対応を行うと、状況をより一層悪化させることがあります。
対応マニュアルを整備し、スタッフ間で共有し、訓練を行っておくことも重要です。
さらに、保護者への緊急連絡体制を文書化し、入会説明時にも共有しておくことで、信頼性の高い運営につながります。
職務著作や勤務の管理
講師が指導に際して作成したプログラミングのコードそのものは、一般的に著作権の対象になりません。
しかしそれに付随する解説文・指導資料・教材構成・図表などには創作性が認められ、講師が作成した場合でも教室ないし運営側に著作権が帰属します。(著作権法第15条)。
講師雇用の際にはその旨を十分に説明し、雇用契約書においても以下のような取り決めを明記しておくとよいでしょう。
- 「職務上作成された教材の著作権は教室に帰属する」旨を明記する
- 外部講師に委託する場合は、著作権譲渡または利用許諾の条件を具体的に定める
- 教材・資料の再利用や他教室での流用を禁止または制限する条項を設ける
また、講師やスタッフが、在任中もしくは退職後に経営情報や個人情報を外部に持ち出すことがないよう、守秘義務や情報管理のルールも明文化しておきましょう。
- 生徒や講師の個人情報を外部に漏らさない
- 教材・カリキュラムの内容を第三者に開示しない
- 教室の運営方針や経営戦略などの内部情報を持ち出さない
さらに、競業避止義務を設定しておくことも、経営ノウハウの流出防止に有効です。
競業避止義務とは、講師やスタッフが在職中または退職後に、同種の教室を立ち上げたり、競合する事業に参加したりする行為を一定期間制限する取り決めです。
ただし、過度な制限は憲法にて保証された職業選択の自由を侵害するおそれがあります。期間・地域・対象業務を合理的に設定し、双方が納得できる形で契約を取り交わしておくことが重要です。
たとえば次のような項目設定が理想です。
- 講師を退職した後は、●年間、同一地域内で同種の教室を開設しない
- 講師を退職した後は、在籍生徒を自らの教室へ勧誘しない
契約・料金設定と消費者保護への配慮
入学手続きの段階で保護者との契約関係をあいまいにしてしまうと、返金をめぐるトラブルやクレームにつながる恐れがあります。
入会時の申込書や利用規約には、料金体系(月次の費用の他、追加費用の有無なども)、返金条件、休会や退会時の取り決めなどを、分かりやすく明記しておきましょう。
- 入会金・月謝・教材費などは総額表示を徹底する
- 途中退会やキャンセル時の返金ルールを明示する
- 無料体験・キャンペーン表示で誤解を招く表現を避ける
看板、ホームページ、リーフレットなど、広報ツールでの誇大な表示にも注意が必要です。
- 「今だけ入会金無料」「今だけ受講料割引」といった表現を、期間の定めなく継続的に使用することは、景品表示法上の違反となります
- 「短期間で必ず上達」「学習成果を保証する」といった、時に誇張となり得るような表現は避けるべきです
消費者保護の観点を意識して、募集営業を実行していく必要もあります。
突発的な訪問営業や電話による強引な勧誘、路上での呼び込みなど、一方的に入会を勧める行為は、地域の方々からの信用を損なうだけでなく、特定商取引法による規制も適用されます。
クーリング・オフ制度が適用され、契約後でも一定期間内(通常8日以内)であれば保護者が無条件で契約を解除できます。
一方、保護者が自身の意思で教室に来校し、通常の流れで受講申し込みを行った場合には、原則的にクーリング・オフ制度の対象外となります。
ただし、こうした場面でも、長時間拘束するなどの強引な勧誘があった場合には、特定商取引法の適用対象となることがあります。
契約等に関する関係法令を正しく理解し、また「社会の一般常識」に反しない行動を徹底していくことが重要です。
個人情報とデータ管理の留意点
生徒/保護者からの提出書類や成績データ、顔写真など、教室では多くの個人情報を扱います。
プログラミング教室では、さらにオンライン学習システムやクラウドサービスを利用する機会も多いため、情報管理リスクが広がりやすい点に注意が必要です。
個人情報を適切に取り扱うためには、次のような基本ルールを徹底しましょう。
- 個人データの保存にはアクセス制限とパスワード管理を徹底する
- 紙資料は必ず施錠保管し、不要になったものは適切に廃棄する
- 教材や受講履歴をデータ共有する場合は、閲覧権限や共有範囲を厳格に設定し監視を行う
- LANの設定により、講師が業務用に使うネットワークに、生徒や訪問者がアクセスできないようにする
また、授業風景や生徒の作品をSNSやウェブサイトに掲載する際には、保護者の同意を得るなど十分な配慮が必要です。
顔や名前などから個人が特定される情報を不用意に公開すると、プライバシー侵害に発展するおそれがあります。
掲載時には、名前を伏せる・撮影アングルを限定するなど、個人が特定されない工夫を心がけましょう。
オンライン授業や発表会を録画・配信する場合にも、同様の配慮が求められます。
他の生徒に提供する映像や音声の中に、生徒の個人情報が特定される情報が入らないよう、慎重にチェックを行いましょう。
まとめ
運営ルールを整えることは、オーナー様の安心につながるだけでなく、保護者からの信頼にも直結します。
ここで触れたポイントを踏まえ、法令遵守と安全運営を両立させる仕組みを整えていきましょう。