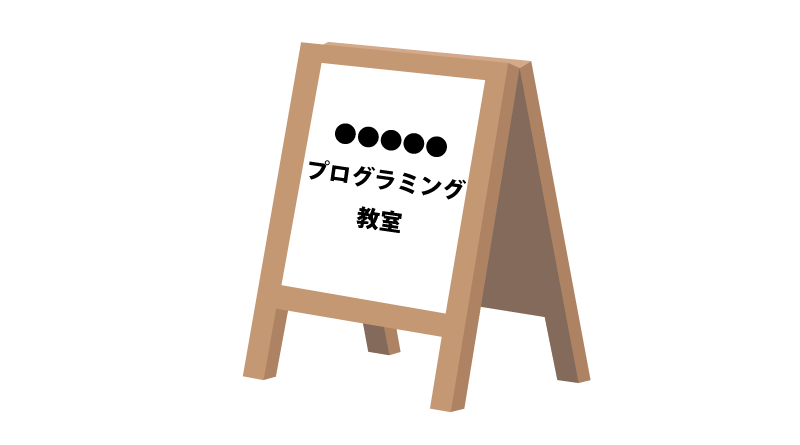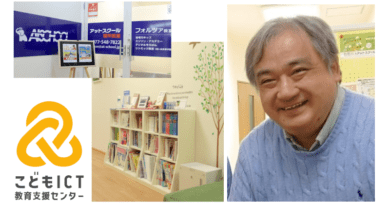新規教室の屋号を考える
新規教室の屋号を考える
このコラムには、いくつかの教室屋号の例が含まれています。
屋号例の表示においては、生成AIツールにて作成した固有名詞から複数の候補を選択し、さらに特定事業者様の商標を無断引用することの無いよう調査を行いました。
しかしながら万が一権利を侵害するとお感じになられた商号がありましたら、ご連絡をいただけますと幸いでございます。直ちに削除ないし修正を行います。
プログラミング教室を開業する際には、屋号について考えていく必要があります。
適切な屋号を選ぶことが、地域で信頼され、長く愛される教室づくりの第一歩となります。
本稿では、教室屋号の決定に至るまでのワークフローについて考えていきたいと思います。
検討事項(1)
地域性を意識した屋号の例
保護者が子どもの習い事を探すとき、多くの場合は「地名+習い事」で検索します。
地域名を屋号に含めた場合には、「●●(地域名) +プログラミング教室」「●●(地域名) + 子ども プログラミングスクール」などのワードにて検索入力を行った場合、上位に表示される確率が高まります。
さらに、Googleマップでの検索表示=MEO(マップエンジン最適化)でも地域名を含む屋号は大きな力を発揮します。
Googleマップ上で「地域名+プログラミング」と検索するとき、地図上に教室が表示されるとともに、「ここなら近い」「通いやすそうだ」と直感的に判断されやすくなります。結果としてクリックやお問い合わせにつながりやすく、実際の来訪にも直結します。
(別途、Googleにビジネス登録をされることが必要です)
さらに地域名を含む屋号を利用することで、単に検索上の有利さだけではなく、地域に根ざして活動していることを、保護者や子どもに理解していただくことができます。
特に地域イベントへの参加や小学校との連携、自治体との協働などの場面にて安心感を感じていただくことができます。
- 「●●(地域名) + プログラミング教室」
- 「●●(地域名) + プログラミングスクール」
検討事項(2)
教育理念を意識した屋号の例
前章では、地域名を含めた屋号というご提案説明をさせていただきました。
しかし、「●●(地域名)プログラミング教室」という単純すぎる名前の場合、教室の理念や運営方針がぼやけてしまうという懸念もあります。
そこを補うために、例えば「教室の理念 + ●●(地域名) + プログラミング教室」といった理念を加筆した形式にするのも良いかもしれません。
例えば、「Start Coding + ●●(地域名)プログラミング教室」と命名した場合、地域に根差した教室であることに加え、「初心者でもゼロから学べる」という運営方針を同時に伝えることができます。
その他にも、いくつかの屋号の例を、生成AIツールに作ってもらいました。
その例から説明をさせていただきます。
- 「はばたきプログラミング + ●●(地域名)教室」
- 「ImagineCode + ●●(地域名)プログラミングスクール」
- 「CodeJourney + ●●(地域名)プログラミング教室」
最新の生成AIはかっこいい名前を考えてくれますね。
「はばたきプログラミング」という名称は、「知識や経験を羽ばたく力に変えて、子どもたちに成長をしてほしい」という願いを感じます。
「ImagineCode」であれば、「想像したことを現実に変えられる」、何だかそんな力が身に付けられそうな気がします。
「CodeJourney」という名前であれば、「学びを一つの旅ととらえ、チャレンジを繰り返しながら成長していく」という姿が想起できます。
理念を込めた屋号を掲げ、さらに体験会や説明会で「この名前にはこうした思いを込めました」とオーナー自らが語ることで、信頼感が増し、共感を呼ぶことにもつながります。
検討事項(3)
命名の制限と守るべきルール
どんなに良い屋号を考えた場合でも、残念ながらそれが使えないという場合もあります。
使ってはいけない屋号
- 登記ができない:
法人化を考える場合、同一住所では同じ商号を登記できません。 - 類似に注意する:
同一商号でなくても、酷似した商号を命名した場合には先行事業者とのトラブルに発展する恐れがあります。また地域の方の誤解を招くおそれがあります。
商標の調査
日本での商標登録は「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で公開されています。
検索欄に考えた屋号を入力するだけで、すでに登録されているかどうかを確認できます。特に教育・IT分野で近い表現が既に登録されていないかを必ずチェックしましょう。
検討事項(4)
インターネットでの表記の意識
ドメインの調査
屋号をオンラインで活用する場合は、ドメイン名(例:●●.jp、●●.com)の空き状況を調べることも欠かせません。
主要なドメイン検索サービスを使えば、希望する文字列が取得可能かをすぐに調べられます。例えば「お名前.com」や「ムームードメイン」などのサービスが便利です。
また、SNSで屋号と同じアカウント名が存在していないかも合わせて確認しておきましょう。
ホームページとSNSのブランド名が統一できない場合、保護者や生徒たちが混乱してしまうことになります。
屋号決定のための手順
最後に、屋号を決める際の流れを整理しておきましょう。
思考の順序はもちろん自由ですが、お困りの場合には参考にしてみて下さい。
- 条件の整理:
上記の検討事項(1)および検討事項(2)を意識して、経営の理念、対象とする学齢、地域との関わり、将来の拡張性などの事業構想を再確認しておく。 - 単語の整理:
1.の条件に即した単語をピックアップする。 - 組み合わせ:
2.を自由に組み合わせ、複数の屋号案をつくる。 - 候補の比較:
覚えやすさ、独自性、拡張性、発音のしやすさなどを基準に候補を絞る。 - 類似商号とドメイン取得の調査:
上記の検討事項(3)および検討事項(4)を意識して、商標、商号登記、ドメイン、SNSアカウントの利用可否を確認する。
まとめ
屋号は、一度決めたら簡単に変えることができません。開業後はチラシやホームページ、看板やSNSなど、あらゆる場面で使われ、地域の人々の記憶に定着していきます。
安易に途中で変更した場合は、それまで積み重ねてきた信頼やブランドを失うこともあります。
だからこそ、屋号は「これから長く付き合っていく名前」として慎重に考えていきたいものです。
未来を見据え、そしてずっと自分自身も愛し続けることができる、そんな素敵な名前を見つけましょう。